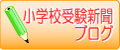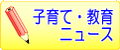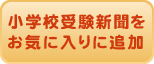|
| 教育ルネサンス (1) 幼児教室 親も子も成長 |
|---|
|
横浜市内の私立小学校入試開始まで1週間に迫った10月中旬、「ジャック幼児教育研究所」横浜元町教室(横浜市中区)では、年長クラスの最終日の授業が行われていた。 大半が、名門私立中学への進学実績で知られる精華小学校(同市神奈川区)を受験するクラス。工作の授業で子どもたちは、参観席で保護者が見守る中、青やオレンジ色のビーズなどをひもに通し、ネックレスを作っていた。 1969年に設立された「ジャック」(本部・東京都世田谷区)は、都内と神奈川、埼玉の両県に計15教室を展開する。ペーパー試験から運動、面接対策まで各種授業をそろえ、年長ではそれらを組み合わせた志望校別クラスがメーン。多くが週1日3コマ(1コマ50分)か週2日5コマ通い、月額7万3500円〜9万4500円だ。ジャック理事の大岡史直(ふみただ)・横浜元町教室長(48)は、子どもに達成感を持たせることを指導の柱として挙げる。「努力してできたという実体験を積ませることが大切。『お受験』合格だけでなく、小学校以降の学ぶ意欲や自信にもつながる」と話す。 小学校受験は、「親の受験」とも言われる。ジャックでは父母向けに講座を開くなど、親の「教育」にも力を入れる。授業参観を求めているのもその一環だ。「入試では、季節の動植物や公衆道徳を問うなど、かつては家庭でのしつけや体験から自然と身につけていた力を見る問題も少なくない。教室が代わりに教えている面もある」と、大岡教室長は明かす。 背景には家庭環境の変化がある。山田昌弘・中央大学教授(53)(家族社会学)は「核家族化や地域のつながりの希薄化が進む中で、母親同士のネットワークもうまく機能しなくなっている」と指摘。「家庭教育の術(すべ)をお金を払って教室に教えてもらうのも時代の流れ」と説明する。 現在精華小1年の長男がジャックに約2年間通った横浜市の母親(38)は、家庭で毎日2時間、宿題を見たほか、絵本の読み聞かせを続けたという。週末は家族でハイキングや昆虫採集に出掛け、自然に接するよう努めた。「教室で学んだおかげで、子育てや家庭教育のあり方を再認識し、母子ともに成長できた」と話している。 首都圏を中心に、小学校受験熱が高まっている。お受験レッスンはどのように展開され、子どもの成長にどんな影響を与えるのかを考える。 メモ
(2010年12月16日 読売新聞から転載)
|
| 教育ルネサンス(2) 働く母のため週末授業 |
|---|
|
「今日は忍者の動きをしましょう。先生をよく見てくださいね」。忍者のお面をかぶった講師が、ゴムひもを跳び、マットの上で転がってみせる。その後、4、5歳児が1人ずつ、手本を懸命にまねしてゴールを目指す。 |
| 教育ルネサンス(3) 女子校「理念」で選ぶ |
|---|
|
教室に2列に並べられた机に母親と女の子が向き合い、色とりどりの薄紙や割り箸を使って花束を作っていた。「次はどの色を使おうか?」と母親、「このピンクがいいなあ」と娘。一緒に手を動かしながら目と目を合わせ、にこやかに会話をしていた。 「幼児教育実践研究所・こぐま会」本部のある恵比寿本校(東京都渋谷区)で、10月下旬に実施された行動観察の授業。東京女学館小学校(同)を志望する年長クラスで、入試で行われる「母子活動」に対応したものだ。 年長は週2回、「基本」と「志望校別」の授業を1コマ(90分)ずつ計2コマ受けるのが平均的。費用は月額8万〜10万円だ。女学館小のクラスは、「志望校別」の3分の1を母子活動にあてている。 講師の桜井紀子さん(57)は、「女子校は、行動観察や面接で母子関係の良好さを見る傾向が強い。その意味で、親子一緒に工作や踊りなどを行う母子活動は象徴的な試験です。出来不出来でなく、話し合い、協力して取り組めるかが問われる」と説明する。 こぐま会では、1983年の設立以来、小学校での学習にスムーズに進むための教育に重点を置く。独自に開発した指導方法で、物に触れたり体を動かしたりしながら、前後、左右といった位置関係を認識・言語化するなど体験を通した学びを行っている。 「発達段階に応じた教育が基本。小学校受験は、その成果を試すきっかけに過ぎない」と、久野(くの)泰可(やすよし)代表(62)。都内に展開する3校に通う約8割が女子だが、「会の教育方針に基づいて指導してきた結果、女子校受験で実績を上げ、女子が多数を占めるようになった」と強調する。 とはいえ、進路指導担当の広瀬亜利子・第1教務部長(52)は「女子校は、求める家庭環境が明確で、特に母親の教育参加を重視する学校が多い。本人の性格や親の考え方が合わないと、学び続けることが困難になる。校風や教育理念を理解して志望校を選ぶよう指導している」と話す。 長女が女学館小1年の母親(40)(東京都品川区)は「一人っ子で大人しく、男の子と一緒に学ぶのは向いていない」と考え、女子校受験を決めた。年中の春からこぐま会に通い、10校ほどの説明会に足を運んだ。女学館にしたのは、「国際理解や伝統文化教育に共感したし、何よりも学校の雰囲気が娘に合っていると感じたから」という。 学校選びの原点が、女子校受験で問われている。 メモ
(2010年12月18日 読売新聞から転載)
|
| 教育ルネサンス(4) 国立付属「タフさ」必要 |
|---|
|
年長クラスの子どもたちが、テープレコーダーから流れる「動物村の運動会」の話を2分程度聞いた後、「お話の記憶」の問題に取り組んでいた。「動物村の村長さんに○をつけましょう」、「運動会で一番目に行った競技に○をつけましょう」。試験官役の講師が質問すると、子どもたちがすばやく答えを書いていく。 11月上旬、「にっけん(日本教育研究所)」(本部・東京都国立市)の仙川教室(同調布市)で「国立大付属小学校合格判定テスト」が実施された。ペーパー試験、行動観察、運動、面接など、計1時間の国立大付属小の入試を想定したテストだ。 1972年に設立された「にっけん」は、都内と神奈川県に計7教室を運営し、国立大学付属小の受験対策で定評がある。ペーパーから絵画・工作や行動観察、運動までバランスよい指導を重視。年長クラスは週2日、計3時間(2コマ)の授業と月1回のテストを受けるのが一般的で、費用は月9万円だ。 国立大付属小は全国に74あるが、多様な子どもを集めることなどから、多くが入試に抽選を含めている。このため、都内の東京学芸大付属の4小学校、お茶の水女子大付属小、筑波大付属小は、軒並み高倍率となっている。私立小の多い首都圏では、国立が第1志望でも、私立と併願するケースが多いという。 「国立は大勢を落とさなければならない分、私立に比べて試験時間が短く、問題が複雑な傾向にある。積極的にきびきびと、自ら考えて行動する力をアピールできるように指導している」と、にっけんの福田菊子・副理事長(67)は説明する。 付属小から大半が付属中学校に進むが、付属高校があっても進学できないことも多く、大学への優先入学制度もない場合がほとんど。系列校進学など進路がある程度決まっている私立と違い、国立は各段階で進路選択や受験に向き合わなくてはならない。 抽選に外れて受験すらできなかったり、試験に合格したものの抽選で外れたり。親子で落ち込む国立ならではのケースが少なくないため、にっけんでは親向け相談も充実させている。福田副理事長は「不合格でもお受験準備は必ず小学校での学びに生かせると、前向きに考えるようアドバイスしている」と話す。 「親子ともにタフさが求められる」(福田副理事長)という国立受験。それでも、教育の質を求め、挑戦者は後を絶たない。 メモ
(2010年12月22日 読売新聞から転載)
|
| 教育ルネサンス(5) 工作 自由にさせ、ほめる |
|---|
|
10月下旬、JR国立駅近くにある「チャイルド右脳教育研究会」(東京都国立市)の教室をのぞくと、子どもたちの元気な声が聞こえてきた。「あっ、崩れちゃうよ」「きれいに飾ろうね」――。 年長クラス最後の工作の授業で、テーマは「お城」作り。色画用紙を切ったり、牛乳パックをセロハンテープで張り付けたりして仕上げていく。ある男子(6)は「高い高いの作ったよ。『よくできました』って、先生やママに言われた」とうれしそうだった。 チャイルドは、1991年の設立。地元国立市を中心に、年中と年長を合わせて約60人と小規模ながら、桐朋学園小学校(国立市)や国立学園小学校(同)など、多摩地区の有名小学校への合格実績で知られる。授業は工作のほか、運動や行動観察、ペーパー対策の指導を週に1回(2時間)行っている。費用は月額約3万円だ。 指導の特徴は、工作に最も多くの時間を割いていること。しかも、入試に必要な知識やテクニックを教え込むことはせず、自由にやらせている。なぜなのか。 「数や言葉などをイメージでとらえる力、つまり右脳を鍛えることが、受験に必要な創造力や思考力、観察力を育むことにつながる。その手法として最も重要なのが工作なのです」と、かつて中学・高校受験塾で数学を教えていた山本寿春代表(62)は説明する。 山本代表によると、自発性を尊重して自由にやらせ、良い点を見つけてほめるのだという。幼児期に自発的に身につけた力は、小学生になってから読解力やひらめきといった基礎能力になるともいう。 東京都立川市に住む桐朋学園小2年の女子は、年少の冬から約1年半通ったお受験教室が合わず、年長の春からチャイルドに移った。母親(34)は、「前の教室は成績を上げるために厳しく指導され、娘を追い込んでしまった。チャイルドでは、良い点をほめてもらい、自分で考えて楽しく取り組めるようになった」と振り返る。 白梅学園大学の汐見稔幸学長(63)(育児学、教育人間学)は、「幼児期に押しつけられて勉強させられると、後に問題を発見、解決する姿勢が失われるばかりか、自尊感情が損なわれる可能性がある」と指摘する。 詰め込みが過ぎると、学ぶ意欲が低下し、燃え尽きることもある。受験が過熱するなか、長所をじっくり伸ばす指導が支持を集めている。 メモ
(2010年12月23日 読売新聞から転載) |
| 教育ルネサンス(6) 幼児教室 関西も熱く |
|---|
|
「お箸を使って、赤いおはじきを自分のお皿に入れてください」。講師の指示に従い、子どもたちが、「生活習慣」の課題に取り組んでいた。 おはじきを上手につまめなかったり、途中で落としてしまったりしながらも、時間内にひとつ残らず移し終えた。 幼児教室「伸芽会」の四条河原町教室(京都市中京区)で、11月20日に行われた4、5歳児の授業。3年保育の「年中」だが、来年の私立小学校受験まであと1年となり、教室では「新年長」として授業がスタートしたばかりだ。「これから1年で様々な実践形式の授業を体験し、大きく力を伸ばしていくのです」と、教務企画局長の飯田道郎さん(50)が説明してくれた。 小学校・幼稚園受験で知られる伸芽会は1956年の設立。本部は東京都豊島区で、首都圏1都3県に26教室、関西2府1県に3教室、計29教室を運営する。教育理念は、その名の通り幼児の興味の芽を伸ばすこと。例えば図形や数量の問題では、折り紙やおはじきで関心を引き、遊びながら学べるよう工夫する。 年長児コースでは、週2日、「総合」「志望校別」の2コマ、計4時間が平均的で、費用は月10万円程度という。 そんな東京の幼児教室の老舗が、四条河原町教室の開校で関西進出を果たしたのは2008年。今年、大阪市と兵庫県西宮市にも教室を設けた。以前も大阪市内の教室と業務提携し、指導方法を提供していた時期があったが、今回は本格的な展開となっている。 背景には、ここ数年、名門私立大の関関同立(関西大、関西学院大、同志社大、立命館大)の付属小学校が相次いで開校し、小学受験熱に一気に火が付いたことがある。 中学受験の「浜学園」(本部・兵庫県西宮市)は05年、未就学児童向けの「はまキッズ」を開設。中学・高校・大学受験の「京進」(本部・京都市下京区)も06年、「京進ぷれわん」を開校し、小学受験指導を始めた。そして、08年、「教室通いへのニーズが高まり、ノウハウを十分に生かせる」(飯田さん)と判断した伸芽会が進出した。 「関関同立」付属小の開校以前も、一定の小学受験層は存在した。しかし、首都圏に比べて私立小の数が少なく、私立の中高一貫校人気や公立高校への信頼が高いことなどから、お受験熱はそれほど高くはなかった。 相次ぐ私立小の開校が、幼児教育への特需をもたらしている。 メモ (2010年12月24日 読売新聞から転載)
|
| 教育ルネサンス(7) 都市と地方に温度差 |
|---|
|
「さあ1分で解くんだよ。スピードを大事に、集中して」。講師の合図で、子どもたちが一斉に国立の福岡教育大学付属の入試の模擬試験に取りかかった。11月中旬、「学習受験社ガゼット」本社のある中央教室(福岡市中央区)の年長コース。試験を受ける12人の表情は真剣そのものだ。 福岡市と福岡県久留米市に3教室を展開する「学習受験社」は、県内で幼児教室と中学受験塾を開校して約40年。小学校受験では、県内の国立、私立への合格実績でトップを誇る。子ども4人に講師1人のきめ細かな指導が特徴で、講師手作りのプリント教材は年間約3000枚に上る。 県内の小学校受験事情について、同社の上迫(うえさこ)純一社長(61)は、「志望校は、福岡教育大付属の3小学校が人気の上位。いずれも中学までで、付属中を経て、トップクラスの県立高校、九州大学へと進学するのが『エリートコース』とされている」と解説する。 受験準備は、かつて家庭でする場合が多かったが、「10年余り前から付属小のペーパー試験が難しくなり、教室通いが目立つようになった。近年、抽選よりも、先に行われる試験で落とす割合が高くなったことも拍車をかけている」と、上迫社長は見ている。 「付属小」「私立」「併願」で1年と2年のコースがあり、最も多いのは「付属小」の1年コース(週1日2時間〜2時間半で、月額約2万3000〜2万6000円)。県内ではこの数年、私立の西南学院小学校や東明館小学校などが開校し、併願が増えているが、あくまでも第1志望は付属小という。 首都圏と関西、北九州以外ではどうか。全国の小学校受験情報をネットで提供する「小学校受験総合研究所」の高橋秀幸代表によると、愛知県や広島県など受験熱が高まってきている地域もあるが、首都圏のような盛り上がりは見られない。 「地方は私立小が少なく、国公立志向が強いため、小学校受験の中心は国立。だが、複雑な問題は出されず、倍率も低いため、友だちと外で遊び、自分で服をたためて、お母さんのお手伝いができれば対応できる学校が多い」と、高橋代表は解説する。 幼児教室で季節感や生活習慣を学び、私立小を目指す。お受験熱は都市部特有の現象かもしれない。 メモ
(2010年12月25日 読売新聞から転載)
|
小学校受験新聞TOP>読売新聞 教育ルネサンス 小学校受験特集