 |
雙葉小学校の合格対策法を教えてください
|
 久野泰可先生からのお答え 久野泰可先生からのお答え
 
雙葉小学校の入試では、よく練られ、工夫された問題が多く出されます。どこかの学校で出された問題を真似して作るのではなく、独自に問題を作成する能力が大変高い学校だと思います。新しい学力観に基づいた問題を常に作り続けてきた学校ですから、よく小学校入試の対策として「どこまで難しい問題をやっておけばよいのか」という質問には、この学校で出題された問題が、その答えになると思います。
よく考えられた問題というのは、パターン練習で解けてしまう問題ではなく、思考力が要求される問題ということです。考える力がなかったら、とても対応できない問題が多く出されています。私たちが見て工夫されたよい問題は、子どもたちにとっては初めて出会う問題、難しい問題ということになります。この辺の事情については、雙葉小学校の問題を数年間にわたって追い続け、何が問われているのか、何が難しいのかなどを分析した「何が合否を分けたのか」(こぐま教育新書)という本にまとめましたので、それをお読みください。
雙葉小学校の問題の難しさを前提に、どのような考え方で対策を考えれば合格につながるのか、そのためには雙葉小学校の入試の特徴をしっかり分析しておかなくてはなりません。最近の入試傾向をふまえ分析してみましょう。最難関校の入試対策ですから、多くの学校の対策にも使えるものと思います。
1.1日目のペーパーテストで、80パーセント以上の得点を取らないと合格は難しい
2.ペーパーが高得点だからといって合格はできない
3.2日目の行動観察テストが重視されており学力主義でない証拠でもある
4.時間制限が厳しく、筆記用具もサインペンだけを使う
5.未測量・位置表象・数・図形・言語と満遍なく各領域の難しい問題が出されるが、
その中でも数・図形・言語が出題の中心になる
6.未測量では「シーソー」位置表象では「移動」の問題がよく出される
7.数の領域は、四則演算に関するすべての問題が出されるが、その中でも「一対多対応」
に関する問題が中心になる
8.「一対多対応」を中心に、他の数の操作とかみ合わせた「複合問題」が多くだされている
9.数の問題は、一場面の絵を使って様々な質問が出題されるが、一番難しいのは、
お話によってその場面を転換してしまい(数が変化する)、そのうえでまた別な質問
をする場合である
10.昨年出された「交換」の問題のように、あるものを仲立ちにして考えなければ解けない
ような問題が多い
11.図形課題は「図形構成」と「図形分割」が中心になるが、三角パズル一つとってみても、
同じ大きさの三角パズルではなく、大きさを変えたパズルで行うというように相当の
工夫が見られる。「図形分割」は補助線の入れ方が問題になる。その感覚は「図形構
成」で養われる
12.論理的思考力が相当求められているが、その根幹を成す思考法は「可逆的思考」であ
り、元に戻す発想(逆思考)や観点を変えて物事を見る見方などを身につけなくては
ならない
13.2日目の行動観察は、物事に取り組む態度や人との関わり方がチェックされ、小学校
生活を送るにあたってのレディネス(準備性)が問われている。自分の意見が言えな
いような子は、この時点で大きなマイナスになる
 
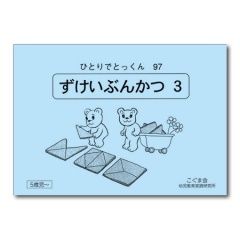 
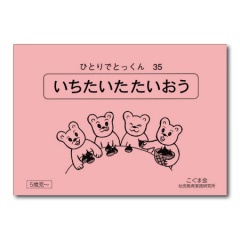 
こうした入試の特徴をふまえ、どのような学習を心がけたらよいのでしょうか
A.考える力を身につけるためにペーパートレーニングを先行させた学習では対応できない。
自分で考え解決する経験を持たせるために、事物を使った試行錯誤の教育がまず何より
も大切である。(事物教育のすすめ)
B.ペーパーの量をこなすのではなく、一枚一枚のペーパーを大事にし、そこで求められて
いる考え方が本当に身についているのかを一度疑いチェックする。その方法は、答えの
根拠を説明させることである。(対話教育のすすめ)
C.思考力が必要な問題の根拠は、小学生の算数で学ぶ文章題の中にヒントがある。それを
分析し、どのような考え方を身につければよいかを教室授業で徹底して行うことが必要で
ある。
(論理的思考の育成)
D.論理的思考力は物事に働きかけていくことを通して身についていくものであり、ペーパー
だけの教育では決して身につかない。
E.解き方を教え込むような指導では、この学校の問題にはとても太刀打ちできない。
何千枚のペーパーをトレーニングしても同じ問題は出ないと考えておく必要がある。
はじめての問題に自分の力で立ち向かうためには、基礎学力を徹底して身につけ、
応用力を高めておかなくてはならない。
F.2日目の行動観察では、集団活動を前提とした経験の豊富さがものをいう。
個別の学習対策だけでは不十分である
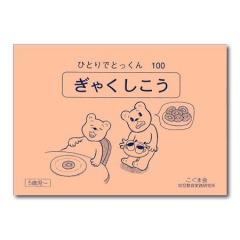 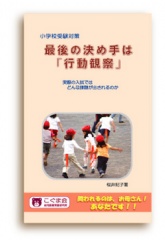
久野先生に質問がある方はこちらから たくさんの質問をお待ちしております!
最新 久野先生のコラムはこちら (こぐま会HP 室長のコラム)
こぐま会ネットショップ はこちら
取り扱い書店一覧
推薦コラム
|